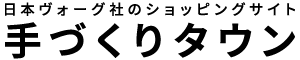秦泉寺由子さん
 1965年京都女子大学卒業後、フラワーアレンジメントを学びに北米に渡り、5年間花修業をするが、アーミッシュ・キルトに出会い衝撃を受ける。そして作ったキルトが「カナダ・オンタリオ・クラフト79」プロビンシャル賞を受賞。1980年帰国と同時に「ジンゼンジヨシコ・キルトグループ」結成。1983、88、92、96年とジャカルタにて「キルト展」開催。各展覧会に出品、個展開催とキルトの道を模索しつつ、1981年にはバリ島に「スタジオジンゼンジ GRASS HOUSE」を設立。1994年から始まった玉川髙島屋の「現代の道具展」は5回を数え、自らのクリエイションの検証の場として、渾身のエネルギーをこめて挑戦している。またジャカルタでは1993年から年4回ボランティアでキルト教室を開き、民間友好の一翼を担っている。著書に「ニードルワークの世界 パッチワークキルト」(マコー社)、「素材から展く新しいキルトの世界 キルトクリエイション」(日本ヴォーグ社)、写真集「MESSAGE FROM GRASS HOUSE」がある。
1965年京都女子大学卒業後、フラワーアレンジメントを学びに北米に渡り、5年間花修業をするが、アーミッシュ・キルトに出会い衝撃を受ける。そして作ったキルトが「カナダ・オンタリオ・クラフト79」プロビンシャル賞を受賞。1980年帰国と同時に「ジンゼンジヨシコ・キルトグループ」結成。1983、88、92、96年とジャカルタにて「キルト展」開催。各展覧会に出品、個展開催とキルトの道を模索しつつ、1981年にはバリ島に「スタジオジンゼンジ GRASS HOUSE」を設立。1994年から始まった玉川髙島屋の「現代の道具展」は5回を数え、自らのクリエイションの検証の場として、渾身のエネルギーをこめて挑戦している。またジャカルタでは1993年から年4回ボランティアでキルト教室を開き、民間友好の一翼を担っている。著書に「ニードルワークの世界 パッチワークキルト」(マコー社)、「素材から展く新しいキルトの世界 キルトクリエイション」(日本ヴォーグ社)、写真集「MESSAGE FROM GRASS HOUSE」がある。
『満月の深夜に観る植物の葉っぱの先端につく大きな水滴の玉、月の光に照らされてきらきらとかがやく様を見ていると、植物は生命力に溢れ、太陽の光の輝きを求め、生命をつないでゆく。その自然の律動がつくった彩はまさしく命のエッセンスである。その命を糸や布に映し、キルト制作の一番のステップとして、素材づくりに一歩すすめた』 秦泉寺さんはバリでのクリエイションの一歩を、こんな美しい文章にしている。 1994年、『キルトクリエイション』(日本ヴォーグ社刊)を上梓してひとつの区切りをつけた秦泉寺さんは、グラスハウスで次なるクリエイションに取り組み始めた。 そんな時、東京・玉川髙島屋での「現代の道具展」の出展で、漆作家の角偉三郎氏とコラボレートすることになった。氏の漆の、美しいフォルムと、何層にも塗りを重ねた力強い朱や黒の横で、自分にとってこれと同じくらいしゃべりすぎず品よく存在感のある色は、と考えに考えた末にたどり着いたのが、白だった。潜在意識に北米のホワイトキルトがあったと思い至ったのは、後のことである。 しかし、白を染めることなど聞いたこともない。六か月間バリのスタジオの目に入る限りの植物や果物で染めてみたが、「全部あかん」。求めるような白は出てこない。敷地内の竹藪で茫然と立ち尽くしていた時、頭の中にかぐや姫のイメージがふっと浮かんだ。「竹でやってみようか」 さっそく竹を細く削り煮出してみたが、竹の子と同じ茶色だ。これは、ベージュにしかならないなと思いつつも、染めて何度も水洗いして干した。二、三時間後に見た時の感激は今もって忘れられない。 「わ、これだ、求めていたものが姿を現した、と。それはもう神様を見たような気がしました。陽の光を受けた白が、プリズムのように内包した彩を放って、角度によって微妙なピンクや緑が透けて見える。布を通して竹の魂を見たと思いました」 ―本文より一部抜粋― キルトジャパン1999年7月号より
 竹で白を染めるなどということを思いついたのは、おそらく世界で秦泉寺さんが初めてだ。そして白の絞りも「そんな事したのあなたぐらい。」と言われた。しかし、秦泉寺さんは竹染めの白から、こんなに様々の表情を引き出した。布をいとおしみ、布を慈しみ・・・・。
竹で白を染めるなどということを思いついたのは、おそらく世界で秦泉寺さんが初めてだ。そして白の絞りも「そんな事したのあなたぐらい。」と言われた。しかし、秦泉寺さんは竹染めの白から、こんなに様々の表情を引き出した。布をいとおしみ、布を慈しみ・・・・。  ナチュラル・ダイの彩りを、ダイナミックにバリの自然の中に還してみた。白だけでなくどの色も、まず竹染めで白く染めた上に色を重ねている。
ナチュラル・ダイの彩りを、ダイナミックにバリの自然の中に還してみた。白だけでなくどの色も、まず竹染めで白く染めた上に色を重ねている。  シルク、木綿、麻、チタンなどの小さな布片を絶妙なバランスでパッチワークしたキルト。赤の上に黄色をかけた深みのあるゴールドだからこそ、拮抗が保たれている。布片の大きさひとつをとっても、これ以上でもこれ以下でもない、ゆるがせないかわいい大きさというものがあるという。クリエイターとしての秀でた感覚が細部にまで行き渡る。
シルク、木綿、麻、チタンなどの小さな布片を絶妙なバランスでパッチワークしたキルト。赤の上に黄色をかけた深みのあるゴールドだからこそ、拮抗が保たれている。布片の大きさひとつをとっても、これ以上でもこれ以下でもない、ゆるがせないかわいい大きさというものがあるという。クリエイターとしての秀でた感覚が細部にまで行き渡る。  竹染めの布が、バリの太陽の下で、内包する彩りを輝かせた。同じキルトが日本で見た時と、確かに違って見える。生まれた地の光と風にさらされ、持てる限りの輝きを発しながら、おだやかな気品をたたえている。
竹染めの布が、バリの太陽の下で、内包する彩りを輝かせた。同じキルトが日本で見た時と、確かに違って見える。生まれた地の光と風にさらされ、持てる限りの輝きを発しながら、おだやかな気品をたたえている。