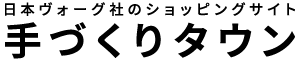服部早苗さん
 東京・田園調布生まれ。中学・高校と演劇に熱中し、女子美術短期大学では日本刺繍を専攻。1978年パッチワーク・スクール「サナエ・アート・スタジオ」を設立、主宰。アメリカン・パッチワークの手法で日本の古典文様の再現を試み、独自の表現世界を拓く。1986年アメリカ・ヒューストンでの世界最大規模の「第12回国際キルト・フェスティバル」に三作品が入選。以降9年連続入賞。『HANDS・ALL・AROUND』にその作品が掲載され、うち「鶴」は表紙作品に選ばれる。1988年オーストリア・ザルツブルグでの「第一回ヨーロッパ・キルト博」で欧米以外で唯一人特別賞受賞。同年カナダ・バンクーバー「ジャパン・フェスティバル」にて作品展開催。1989年ニューヨークでの「ザ・グレート・アメリカン・キルト・フェスティバル2」展で日本人で唯一人入選。同年「第15回国際キルト・フェスティバル」AIQA国際コンテストで金賞受賞。1990年全編ドイツロケを敢行した映画作品「服部早苗 美の世界」完成。国内外での数多くの賞受賞と共に、世界各国で作品展を開催。著書に『服部早苗 ジャパン・キルト』京都書院刊、『ジャパン・キルト 服部早苗美の世界』中央公論社刊など。
東京・田園調布生まれ。中学・高校と演劇に熱中し、女子美術短期大学では日本刺繍を専攻。1978年パッチワーク・スクール「サナエ・アート・スタジオ」を設立、主宰。アメリカン・パッチワークの手法で日本の古典文様の再現を試み、独自の表現世界を拓く。1986年アメリカ・ヒューストンでの世界最大規模の「第12回国際キルト・フェスティバル」に三作品が入選。以降9年連続入賞。『HANDS・ALL・AROUND』にその作品が掲載され、うち「鶴」は表紙作品に選ばれる。1988年オーストリア・ザルツブルグでの「第一回ヨーロッパ・キルト博」で欧米以外で唯一人特別賞受賞。同年カナダ・バンクーバー「ジャパン・フェスティバル」にて作品展開催。1989年ニューヨークでの「ザ・グレート・アメリカン・キルト・フェスティバル2」展で日本人で唯一人入選。同年「第15回国際キルト・フェスティバル」AIQA国際コンテストで金賞受賞。1990年全編ドイツロケを敢行した映画作品「服部早苗 美の世界」完成。国内外での数多くの賞受賞と共に、世界各国で作品展を開催。著書に『服部早苗 ジャパン・キルト』京都書院刊、『ジャパン・キルト 服部早苗美の世界』中央公論社刊など。
そんな子育て中のある日、アメリカ民族展でパッチワークを見た時、そのダイナミックなスケールの大きさに感動した。女子美時代の卒業制作で、五十号の日本刺繍に一年もかかり、遅々として進まずため息が出た経験があったので、日本刺繍に取ってかわる物を見つけたと思った。
しかし当時はキルトの指導書も道具もない頃。まったくの独学で手なぐさみにちょこっと作っては、近所の人に請われて家で教えたりしていた。そしていよいよ下の娘が幼稚園に入るのを機に一念発起、半年間で大小とり混ぜ百作品を作った。
それまでのゆったりした生活が夢のように、本来持っていた創作意欲に火が付いた。一日二十時間は針を持つという、まるで火山の爆発のような激しさだった。作品展は大反響で、一挙に二百人の生徒を持つことになる。こうして「サナエ・アート・スタジオ」を設立したのが1978年の時だった。
あらん限りのエネルギーを注いで実現させた作品展だったが、終えてみると、何だか不満が残った。そこに並んだ作品たちは、まぎれもなく自分が命を削って作ったものだが、デザインはアメリカン・パッチワークのコピーだという事実。
私は日本人で、日本には独自の素晴らしい伝統文様があるではないか。そうだ、日本刺繍の家紋をパッチワークにデザインしてみよう。ここから服部さんのパッチワークの根幹をなす、日本美の追求が始まった。現在キルトの世界に、ジャパンキルトという流れは定着しているが、服部さんの着眼は早かった。 これらの作品が雑誌にも掲載され始め、その注文に応じる作品作りに追われる日々が続いた。すると今度は何か違う、これは本当に自分が作りたいものとは言えないという思いに捕らわれ始めた。そこで雑誌の仕事はいっさい断り、自分の創作だけに目標を定めた。 この辺の思い切りの良さは、形態は違うとはいえ、十年やってきた演劇や日本刺繍などの創作活動が、自分の生き方そのものになった人の強さ、潔さである。家紋から入った日本の伝統文様は、古本屋で見つけた切り紙細工の本や古典文様帳がヒントとなり、次々にオリジナリティの高い作品を生み出していく。 ―本文より一部抜粋― キルトジャパン2000年1月号より
あらん限りのエネルギーを注いで実現させた作品展だったが、終えてみると、何だか不満が残った。そこに並んだ作品たちは、まぎれもなく自分が命を削って作ったものだが、デザインはアメリカン・パッチワークのコピーだという事実。
私は日本人で、日本には独自の素晴らしい伝統文様があるではないか。そうだ、日本刺繍の家紋をパッチワークにデザインしてみよう。ここから服部さんのパッチワークの根幹をなす、日本美の追求が始まった。現在キルトの世界に、ジャパンキルトという流れは定着しているが、服部さんの着眼は早かった。 これらの作品が雑誌にも掲載され始め、その注文に応じる作品作りに追われる日々が続いた。すると今度は何か違う、これは本当に自分が作りたいものとは言えないという思いに捕らわれ始めた。そこで雑誌の仕事はいっさい断り、自分の創作だけに目標を定めた。 この辺の思い切りの良さは、形態は違うとはいえ、十年やってきた演劇や日本刺繍などの創作活動が、自分の生き方そのものになった人の強さ、潔さである。家紋から入った日本の伝統文様は、古本屋で見つけた切り紙細工の本や古典文様帳がヒントとなり、次々にオリジナリティの高い作品を生み出していく。 ―本文より一部抜粋― キルトジャパン2000年1月号より
 「大牡丹唐草」150×155cm 1997年
「大牡丹唐草」150×155cm 1997年
日本の伝統工芸<漆>の美しさをイメージし、金、茜、黒を基本色に構成。大牡丹と唐草はシルクサテンの黒と金襴のヘクサゴンはぎをアップリケし、漆の中に凛と映える螺鈿の様。 「ルードウィッヒの宝石」 200×370cm 1994年
「ルードウィッヒの宝石」 200×370cm 1994年
国家財政を傾けてまで芸術と美を愛したルードウィヒⅡ世に感動し、感謝したいと思った純粋な一念が創作の原動力になったと語る作品。 「ロマネスク桜」 150×160cm 1992年
「ロマネスク桜」 150×160cm 1992年
服部さんの創作コンセプトの一つに、日本の古典文様を使ってヨーロッパのゴージャスな美しさを再構築するというシリーズがある。上は亀甲文様の中に桜がのぞく“のぞき桜”。桜合わせで3枚をデザインしているので毘沙門亀甲にも見える。 「糸はデュアル・デューティー、針も道具もまったくこだわりません」。言葉のとおり、アトリエにそのこだわりは感じられない。しかし、でき上がった作品はきれいな仕上がりだ。
「糸はデュアル・デューティー、針も道具もまったくこだわりません」。言葉のとおり、アトリエにそのこだわりは感じられない。しかし、でき上がった作品はきれいな仕上がりだ。