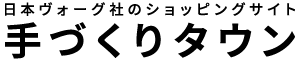松山敦子さん
 茨城県土浦生まれ。1981年パッチワークを習い始める。1984年パッチワークスクール「ハーツ&ハンズ」に入学し、故野原三輝氏に師事。1989年「キルトスタジオA・two」設立。同年から土浦市・つくば市を中心にしたキルト展を開催。1990年「私の部屋」12月号で作家としてデビュー。1998年「日本のキルトアーティスト123人展」(銀座三越)に出品。2002年1月「東京国際キルトフェスティバル」(東京ドーム)“日本のキルト作家新作展”に出品。多くの雑誌や作品展で活躍中。著書に「松山敦子のロマンティックパッチワーク」(主婦と生活社)、「松山敦子のかわいいパッチワーク・花アップリケがいっぱい」(日本ヴォーグ社)がある。
茨城県土浦生まれ。1981年パッチワークを習い始める。1984年パッチワークスクール「ハーツ&ハンズ」に入学し、故野原三輝氏に師事。1989年「キルトスタジオA・two」設立。同年から土浦市・つくば市を中心にしたキルト展を開催。1990年「私の部屋」12月号で作家としてデビュー。1998年「日本のキルトアーティスト123人展」(銀座三越)に出品。2002年1月「東京国際キルトフェスティバル」(東京ドーム)“日本のキルト作家新作展”に出品。多くの雑誌や作品展で活躍中。著書に「松山敦子のロマンティックパッチワーク」(主婦と生活社)、「松山敦子のかわいいパッチワーク・花アップリケがいっぱい」(日本ヴォーグ社)がある。
布大好き、針仕事大好きな少女だった松山さんは気がついたらキルト作家になっていたという脱力型。大きな目的意識や野望とは無縁の、「なるがまま」人生だったというが、風に逆らわない柳が思わぬ強さを秘めているように、松山さんの作品の根底には「好きな世界」へのこだわりが感じられる。キーワードは「カワイイ」。この、漠然としてつかみ所のない可愛いという感覚こそ、松山さんのキルト制作の根幹になっている。その表現素材として欠かせないのが、1930~40年代の布、フィードサック(飼料袋)だった。松山さんとフィードサックとの出会いは、1987年ビクトリア・ホフマンさんが来日したときにアンティークキルトを見に行って、ひと目で心奪われたと言う。アメリカに行き始めて2回目からは、フィードサックといえばどれも欲しくなるほどのめり込んでしまった。
キルトの作業のなかで一番好きなのは、キルティングしているとき。「キルティングは、ひたすらチクチクと針を進めるだけで、あとは仕上がりを待つばかりでしょ。一番幸せ感にひたれる時間なんですよ」。キルトのデザインとしてはトラディショナルが好きで、なかでも三角、四角つなぎのような、一枚の型紙でできるようなものが好きだと言う。大作はだいたい締め切りぎりぎりにしかできないので、完成した日の一夜だけそれを寝具に掛けて、淡い夢を期待して幸せに浸る。
「これから先もずっと今のような生活だと思います。もう一生かかっても使いきれないほどのフィードサックがありますから、とにかく作品にしていかなくちゃと思ってはいるのですが…。これだけは人に絶対渡したくないし、小さく切るのもいやだし、本当に悩みの種です」
本文より─部抜粋─ キルトジャパン2002年11月号より
 花のブローチをいっぱいコラージュした、バッグ、クッション、ポーチの小ものたちと、キッチン仕事が楽しくなるキュートな色合いのなべつかみ。ラブリーなデザインには定評がある。
花のブローチをいっぱいコラージュした、バッグ、クッション、ポーチの小ものたちと、キッチン仕事が楽しくなるキュートな色合いのなべつかみ。ラブリーなデザインには定評がある。
 布棚には、大好きなフィードサックの布が色ごとに整理され、きれいに並んでいる。
布棚には、大好きなフィードサックの布が色ごとに整理され、きれいに並んでいる。
 アメリカで買い求めた、飼料、小麦粉、砂糖袋のいろいろ。ラベルをはがして洗濯をする。
アメリカで買い求めた、飼料、小麦粉、砂糖袋のいろいろ。ラベルをはがして洗濯をする。
 『Berry Berry Strawberry』2001年制作 185×167cm
東京ドームで開催された、国際キルトフェスティバルの際に制作。フルーツの柄、特にイチゴ柄の布が好きでコレクションをしていたので何とか、それを生かしたいと思い制作した。先にタイトルが決まり、ログキャビンのパターンをいろいろ変えて、イチゴのモチーフと組み合わせている。
『Berry Berry Strawberry』2001年制作 185×167cm
東京ドームで開催された、国際キルトフェスティバルの際に制作。フルーツの柄、特にイチゴ柄の布が好きでコレクションをしていたので何とか、それを生かしたいと思い制作した。先にタイトルが決まり、ログキャビンのパターンをいろいろ変えて、イチゴのモチーフと組み合わせている。